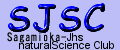|
缶でできるわたがし機
お祭りとかでよく見かけるわたがしの材料は砂糖だけ、というのはご存じですか?
10月22日:穴のサイズが1.5mmになっていたのを修正しました。
*わたがしは,さまざまな呼び方をされているため,本文中では,わたあめ,綿飴,綿あめ,わたがし,綿菓子などと,
あえて表現をゆるがせています.ご了承ください.
綿菓子は知っている方もいると思いますが、そうです。原料はただ一つなんです。
部活では遠心力の実験をかね、缶で誰でも出来る(とおもいます)わたがし機を作りました。
ちなみに、こちらに他の方が作ったもっとわかりやすい図があります。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/4764/52/530309.htm
を参照してください。
先に今回作った綿飴製造機の簡単な情報を表にまとめます。
| 部活で作成した綿あめ製造機の材料 |
|---|
| 使用さとう | ざらめ |
|---|
| 使用缶 | 缶詰の缶 |
|---|
| 穴の数 | 大きめ(2.5mmを使用)の30個くらい |
|---|
| 熱しかた | 回しながら熱する |
|---|
| 回転モーター | DC12Vクーリングファン |
|---|
|
| 自作わたあめ製造機の原理 |
 まず、側面に数カ所穴を開けた缶に砂糖を入れ、溶かしその状態で缶を回すと、 まず、側面に数カ所穴を開けた缶に砂糖を入れ、溶かしその状態で缶を回すと、
遠心力で穴からわたがしのひもが出てくるということです。
この原理だけを説明するととても簡単にできるように思えます。
もちろん簡単にもできます。ただ今回作成したのは、文化祭で実演することも考え、
ちょっとワンランクアップで作成しよう、と考えました。
図の方法では、カセットコンロなどで熱し、
大きな鍋などのなかでドリルを回すと缶の穴から遠心力を使いわたがしが出てきます。
 部活で考えたのはいちいち動かさず本物っぽくしようと考えました。 部活で考えたのはいちいち動かさず本物っぽくしようと考えました。
それが左のようなものです。まずいろいろな部品があるので説明しますと、
缶・・・缶詰の缶です。側面に30個くらい穴があいています。
回転モーター・・・秋葉原で購入の100円のクーリングファンです。これがドリルの代わりです。ちなみに電源は理科で使う電源装置でDV12V以下で状況に合わせて電圧を変えています。
ガスバーナー・・・アルコールランプよりもすぐ火を消せる点で優れているので使用しました。
ぶれ止め・・・この回し方だと多少中心がずれるだけでものすごくぶれます。それを提言する役目です。理科で使うスタンドを改造したものです。
箱置き・・・出てきたわたがしを受けるための箱を置く台です。
▲写真や青字の文をクリックすると拡大します
|
| 完成までの道のりPart-I・あきかんはあかん |
まず最初にサイダーの缶で試してみよう、ということになり、作成開始しました。
多くの缶にはコーティングしてあって、ビニールやペンキがもえると、
ダイオキシン+煙が発生すると聞いていました。ものは試し。
熱したところ、やはり大量の煙が発生しました。おまけに臭いです。
我慢しつつ、ヤスリも使いながらペンキハガシが完了しました。
そこでもう一度火にかけたところ、「ボン!」という音と共に爆発しました。
まだ残っていたようです。爆発といっても超小規模ですが・・・
缶によっては平気なのもあるそうですが一番いいのは東急ハンズで
ちょうどいい缶を買ってくる、ということです。
ちなみに、部活では下図のような缶詰の缶を使用しました。ラベルが紙の缶詰がオススメです。
というのも缶詰も場合によってはコーティングしてあるのでご注意ください。
ここからわかったこと→缶ではコーティングしてあってわたがしのような食料には向かない。
紙ラベルの缶詰または買ってきた方がよい。
  | | 今回、使用した缶 |
|---|
|
| 完成までの道のりPart-II・側穴はちょっと大きめに |
砂糖は回すと外側へ行きます。それで砂糖が穴から出てきます。
砂糖を出すための穴を側面に開ける必要があります。
本物のは網状になっているそうです。ここでは穴を開けることにします。
穴が小さいと一回やるだけで砂糖が詰まってよくありません。
今回は2.5mmで行いました。これか3mm位がいいと思います。
空ける場所ですが、砂糖を入れたときの嵩の一番上から・・・
回すと外側と共に上にも行きます。そこも考えて開けてください。
缶の大きさによりますが個数は20~40の間くらいだと思います。
ただ、缶を選ぶとき余り直径が大きすぎないものを選んでください。
ここからわかったこと→穴は2.5mm位のものを30個くらいで間隔を均等に開ける
|
| 完成までの道のりPart-III・中心を求めて |
缶の底に開ける穴はど真ん中でなければ大きくぶれてよくありません。
ということでできるだけずれないように試行錯誤しました。
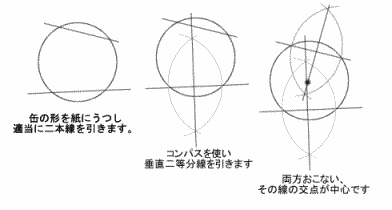
このようにして中央を求めます。
次に穴を開けるとき十文字切りという刃を使い穴を開けます。
するとほぼ中央になります。
ここからわかったこと→底の中心をしっかりと開ける。方法はコンパスを使い中心を求め、
きり・千枚通しなどで穴を開ける
|
| 完成までの道のりPart-IV・背の低い缶には蓋を? |
PartIIでちょっと説明しましたが回すと多少砂糖は上に上がります。
そこで上に飛び出さないように蓋をつけましょう。
PartIの写真を見れば感じはわかるかと思います。
大きな缶の底をくりぬいて加工して蓋にしました。
ただ、今回使用した缶詰の缶では砂糖がそこまで上に行きませんでした。
ここからわかったこと→背の高い缶では蓋は必要ない
|
| 完成までの道のりPart-V・固定は工夫が必要 |
実はこれはとても悩んだものの一つです。
回転モーターであるファンと棒をどのようにくっつけるか・・・
学校中をあさり、家中をあさり使えそうなものを探し回りました。
 すると、家に壊れたドリルの先がありました。 すると、家に壊れたドリルの先がありました。
それを両面テープでファンと固定し、
さらに周りにセロファンテープなどで固定しました。
中心にこの部品を置かないと何も始まりません。コレガとても苦労しました。
ここからわかったこと→意外と家などのにある廃材でちゃんとしたものがつくれる
|
| 完成までの道のりPart-VI・箱 箱 箱 |
だんだんと形になってきました。ここまで約1ヶ月なんども失敗しながらきました。
缶の穴からわたがしが出てくるのでもちろんそれを受ける箱が必要です。
 ひとまず学校から段ボールを物色しそれにアルミホイルを張りました。 ひとまず学校から段ボールを物色しそれにアルミホイルを張りました。
できるだけ大きな段ボールの方がいいことがわかっています。
遠心力を使い缶の穴から出てくるわたがしは
割箸にくっつくまでにできるだけ冷えた方がいいのでしょうか?
二つつなげればできますが今回は一つの段ボールでやりました。
ドリルでやる方は段ボールでなくとも洗面器などでやってみてください。
別に風呂の浴槽でやるのもいいです。
ただ水に長いことつけとかなくては
砂糖が落ちません。ご注意ください。ちなみに段ボールなど受けがないと
そのうち気づくと思いますがズボンがべったべたのネッチョネチョになります。
ここからわかったこと→受けの箱やバケツ等はできるだけ直径がでかいものを奨めます。
|
| 完成までの道のりPart-VII・地震を防げ! |
この問題は本当に難しいです。完成した今でさえまだ完全解決でありません。
ブレです。ちょっとでも曲がっていたり中心からずれていると頭をふりだします。
電圧を下げ回転を落とすと遠心力で出るわたがしは飛ばなくなってしまいます。
そこで、理科室にあった実験用のスタンドを使うことにしました。
スタンドの棒はとても長いので切らなくてはなりません。
------余談-----
実はこの鉄の棒を切るとき大変なことが起きていました。
先生に許可をもらい木工室で鉄ノコで切ることにしました。
技術科担当の先生を探し、棒を持ち学校中を歩きます。
よく考えたら外では今までに体験したことのない程の雷雨です。
雷が落ちる瞬間を何十本も見ました。間近です。
実は町のほとんどの道路が冠水し雷は町中を直撃。
おかげでPC教室でルーターが壊れ長い間インターネットができなくなったそうです。
校舎の外に出て先生を捜し屋根のあるところを歩いていました。
すると正面から歩いてきた別の先生がそんなの持ってると落ちるぞ!といって逃げ去りました。
このときやばい、と感じ、先生探しをあきらめ校舎内に戻りました。
やっと木工室に入れ万力に棒を固定して切ろうとします。
しかし、この万力がある場所、それは外に限りなく近い窓から50cm位のところ。
雷の落ちるところを見ながら切っていました。
何とか丸焼きにならずいきて切り終わりました。
------余談終わり-----
棒を切ったら簡単に軸を固定することができました。
しかし、この固定台があるにもかかわらずぶれてしまいます。
この問題は難しくていまも解決策を探している状態です。
ここからわかったこと→ブレを防ぐには重いものなどでしっかり固定
|
| 完成までの道のりPart-VIII・そこが問題なんだよな。 |
底が問題なんです。今回使用した缶はとても底が薄くて、
すぐ曲がってしまいます。
鉄板を底に張ったりすると解決かと思いますが、いまだ未解決です。
毎回わたがしを作る前にチューニングします。
ただ、このわたがし機、お客さんが来ると必ずと言っていいほど調子が悪くなるんです。
本番は成功することを祈っています。
ここからわかったこと→缶を選ぶときはできるだけそこが厚いものを!
|
| 完成までの道のりPart-IX・完成 |
このページでは表せないほどの苦労でとうとう完成しました。
 (写真はわたがし部分をライトアップしてあります) (写真はわたがし部分をライトアップしてあります)
見てのとおりあまり大きくはできません。
いっぱい苦労した成果がこんな感じです。
あくまでも食べることが目的ではありません。
遠心力でこんな事ができるんだ、という実験です。
ここで紹介したのは難しいやり方ですが、
違う方法でやれば家でも簡単に作れます。
そもそもわたあめを作ろうと考えたのは、夏休み中に
ほぼ毎年行く
秋田のゆきの小舎という宿で教えてもらったものです。
それを部活でアレンジしてチャレンジしたわけです。
是非みなさんも作ってみては?
お祭りなどで使われている、わたがし製造機は火でなく電熱線(ニクロム線)が
使われているそうです。砂糖を入れる量は大さじ一杯。
|
| こんなことも~あとがき~ |
これにかけた費用、実に100円です。クーリングファン代だけで、
後はあるものですべてできました。
実はこのわたあめ機を作成するに当たっていろいろな先生の協力もありました。
例えばどういう形にすれば熱しながら回せるだろうか、など。
その中で顧問が妙に本物のわたがし機について詳しく語ってくれます。
何でそんなに知っているか尋ねたところ、「うちにあるもん」
この先生の家にはわたがし機があるそうです・・・
また作っているときガスバーナー側面はものすごく熱くなります。
実験中にちょっとさわってしまいました。
何度もやけどしたことはありますがこんなに熱いのは、はじめてです。
すぐに冷やしましたが水ぶくれになりその日は夜までずっと熱くいたかったです。
みなさん、やけどをしないように十分注意してください。
情報提供
ゆきの小舎の常連さん
各種ホームページ
アイディア提供
顧問の文男先生(ペンネーム)
技術科のO先生
数学科のO先生
部品提供
理科のS先生
技術科のO先生
某自動車メーカーさん
アキバのジャンク屋さん
|
| 本文中で使われなかった写真集 |
クリックすると拡大します。
 

 

|
| ▲ページトップへ
|